
第一次世界大戦: 余波
第一次世界大戦の後に課された巨額の賠償金は、物質的に多くが破壊された戦争によって直接もたらされた1920年代のヨーロッパの全面インフレ時代と相まって、1923年にはドイツのライクスマルクの急激な超インフレをきたしました。この超インフレ時代は、大恐慌(1929年から)の影響とともに、ドイツ経済の安定性を大きく揺さぶり、中流階級の個人貯蓄を無にし、失業率に拍車をかけました。
このような経済的な混乱は、社会不安の増大につながり、もろいワイマール共和政を揺るがしました。ドイツの周縁化のための西ヨーロッパ列強による取り組みは、ドイツの民主的指導者たちを孤立および弱体化させ、再軍備と拡張によるドイツの威信の回復のニーズを強調しました。
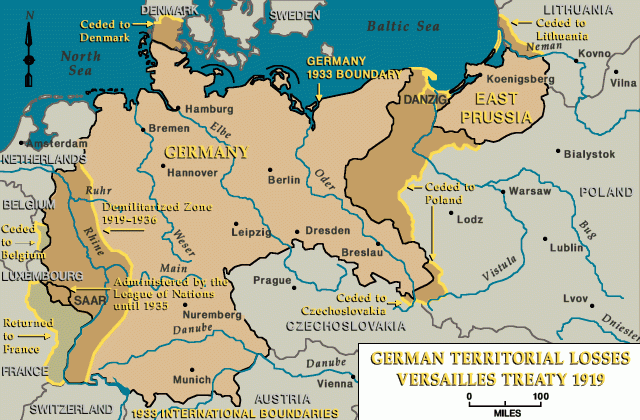
第一次世界大戦後の社会的および経済的な大混乱は、ドイツの未熟な民主主義を揺るがすとともに、ワイマールドイツに過激派右翼の政党を多数生み出しました。ベルサイユ条約による厳しい規定に関連して、特に弊害をもたらしたのは、ドイツは「11月の犯罪者」(新しいワイマール政府の発足を支持し、ドイツが強く望んでいた和平調停を行ったが、ベルサイユ条約で悲惨にも終結した)によって「背後から刺された」という信念が大衆に広まったことでした。
ドイツ人の多くは、ドイツ皇帝の退位を称賛するとともに、議会の民主改革を歓迎し、休戦を喜んだことを忘れていました。彼らが覚えていたのは、外国の軍隊がドイツの地に足を踏み入れる前に、ドイツの左翼社会主義者、共産主義者、およびユダヤ人がドイツの名誉を屈辱的な平和と引き換えにしたことだけです。このDolchstosslegende(匕首伝説または背後からの一突き)は、ドイツの退役した指揮官たちによって始められ、煽られました。この指揮官たちは、1918 年にはドイツが戦争を遂行できなくなったことを十分に理解し、ドイツ皇帝に講和を求めるよう助言した者たちでした。これにより、ドイツの不安定な民主主義を維持しようと強い熱意を抱いていたドイツの社会主義者および自由主義者はますます信用を失っていきました。
Vernunftsrepublikaner(理性のある共和派)である歴史学者のフリードリヒ・マイネッケやノーベル文学賞受賞作家のトーマス・マンは、当初は民主改革に反対していました。しかし、悪いものの中でも一番ましな代替案として、ワイマール共和政を支持せざるを得ないと感じるようになりました。彼らは、同胞たちを過激派の左翼または右翼への極化から遠ざけようとしました。必要であれば、武力によってベルサイユ条約を改定するというドイツ国家主義右翼による約束は、有徳者の間に受け入れられていきました。一方、ロシアにおけるボルシェヴィキ革命と、ハンガリーにおける一時的な共産革命(ベーラ・クン)、およびドイツ国内での革命(スパルタクス団蜂起など)の影響が残る中で、目の前に迫った共産主義の脅威による不安から、ドイツの政治に対する感情は右翼の大儀へと明らかに移っていきました。
政治的左派からの扇動者たちは、政情不安を引き起こしたとして、重い実刑判決を受けました。一方、バイエルンの政府を退けて、1923年11月のビアホール一揆で「民族革命」を開始しようとしたナチ党のアドルフ・ヒトラーのような過激派右翼の活動家は、死刑に相当する反逆罪に対して懲役5年のうち9か月の刑期を務めただけでした。服役中にヒトラーは、政治綱領『Mein Kampf(わが闘争)』を書きました。
第一次世界大戦とその厳しい講和条件がもたらした社会的不安や経済的不安による困難、そして、ドイツの中産階級における共産主義による政権奪取の可能性に対する現実的な恐れは、ワイマールドイツにおける多元的民主主義の解決策の弱体化につながりました。さらに、国民の独裁主義への願望もますます強まりました。不幸にもドイツの有権者は、最終的に、アドルフ・ヒトラーとその国家社会主義政党にこの類のリーダーシップを見出しました。第一次世界大戦の敗戦国をはじめとして、東ヨーロッパでも同様の条件が右翼独裁主義および全体主義体制を助長し、そのうち、強烈な反ユダヤ主義や地域の少数民族への差別を容認および黙認する動きが高まりました。
最後に、第一次世界大戦で多くの命が失われたことは、元交戦国の多くで文化的絶望としか言いようのない現象をもたらしました。国際および国家の政治に対する失望と、政治指導者や官僚に対する不信感が、壊滅的な4年間の戦争の惨状を目の当たりにした国民に広がっていきました。ほとんどのヨーロッパ諸国では、一世代すべての若者を失ったも同然でした。1920年の作品『Stahlgewittern(鋼鉄の嵐の中で)』を書いたドイツ人作家エルンスト・ユンガーなどの一部の作家は、戦争の猛威と紛争の国家的状況を賛美しましたが、前線部隊の経験をとらえ、戦争から戻っても平時に適応できず、戦争の恐ろしさを直接見ていない国内の人々に不幸にも誤解された「失われた世代」の疎外感を表現したのは、エーリッヒ・マリア・レマルクの1929年の傑作『Im Westen nichts Neues(西部戦線異状なし)』で描かれた塹壕戦の鮮明で現実的な物語でした。
一部の社会では、政治と戦争に関する無関心と失望感により平和主義感情が高まりました。米国の世論では、孤立主義に戻ることを望みました。米国上院がベルサイユ条約の批准およびウィルソン大統領が提案した国際連盟への米国の加盟を拒否した根底には、このような国民感情がありました。ドイツの一世代にとってのこの社会的疎外と政治的失望感は、ドイツ人作家ハンス・ファラダの『Little Man, What Now?(小さな男-さて、どうする?)』に描かれています。これは、経済危機と失業の混乱に巻き込まれ、政治的過激左派および右派の誘惑の言葉に弱いドイツの「ごく普通の人」の物語です。ファラダの1932年の小説では、彼が生きた時代のドイツが正確に描かれています。それは、経済的不安や社会的不安で動きがとれず、政治的スペクトラムで二極化されている国でした。この混乱の原因の多くは、第一次世界大戦および大戦後の余波に根差しています。ドイツが選んだ道は、数年後のさらに破壊的な戦争へとつながっていきました。

